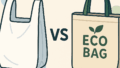――スタジアムの照明が、夜空に向かってまっすぐ伸びていた。
風は静かで、しかしどこかざわつく。今日が最後だ――誰もがそれを知っていた。
ピッチの中央に立つ俺の足元には、まだ温かい芝生の感触がある。
スタンドには、これまで見たことのないほどの人々が集まっていた。
サポーターの声は、いつもの応援歌ではなく、どこか祈るような、別れを惜しむような響きを持っていた。
「行ってこい。最後まで、お前らしくな」
キャプテンの手が肩に置かれる。
彼とは10年以上、同じユニフォームを着て戦ってきた。
俺は静かに頷いた。
――今日が引退試合。
そして、まだ俺はゴールを決めていない。
*
サッカーを始めたのは6歳のときだった。
走ることが好きだった。ボールを追いかけていると、時間なんて関係なくなった。
中学、高校、そして日本のユースを経て、プロになった。
順風満帆だったわけじゃない。
怪我もした。スタメンを外れた時期もあった。
監督と衝突して、ベンチに座り続けたこともある。
けれど、いつだってピッチに戻ってきた。
それは、ゴールを決めたときの音――
あの瞬間の歓声が、俺の命を燃やしてくれたからだ。
グラウンドに立つ。それだけで、俺は生きていると感じられた。
*
「ラスト5分です。交代、どうしますか?」
ベンチにいるコーチが監督に問いかける。
「このまま行く」
監督は短く言い切った。
――俺のプレーで、まだこの試合は終われない。
スコアは1−1。
このまま引き分けでも、誰も文句は言わないだろう。
チームはすでに優勝を決めている。
今日は消化試合であり、セレモニーの日であり、そして――
俺がサッカー選手として過ごす、最後の夜だった。
*
ピッチに戻った瞬間、観客の声が一段と高まった。
「頼むぞ!」
「もう一度だけ見せてくれ!」
「お前のゴールが見たいんだ!」
――わかってる。
俺だって、まだ決めたいんだ。
ボールが回ってくる。
トラップして、スルーパス――だが合わない。
焦りはない。
むしろ、時間がゆっくりと流れていく。
残り3分。
ボールは相手のディフェンスラインを揺らし、やがて味方のボランチへ戻る。
俺は前線で、静かに呼吸を整えた。
1度目のチャンスは過ぎた。
2度目が来る保証なんてない。
でも――
サッカーは、いつだって奇跡のスポーツだ。
*
残り1分。
味方のサイドバックがボールを運ぶ。
相手ディフェンスはすでに体力を失い、足が止まっている。
「来い……来い……!」
心の中で叫びながら、俺は最終ラインのわずかな隙間を探す。
ボールは中盤を経由せずに、浮き球で前線へ――
来た。
俺は相手DFの背中に身体を預け、一瞬、逆方向に動くふりをしてから、前へ抜け出した。
ラインは割っていない。
飛び出し。
トラップ。
右足のインサイドで前へ。
――ゴールまで、約18メートル。
相手GKが飛び出してくる。
時間が止まったようだった。
俺は足を振りかぶった。
スパイクが芝を捉える音が聞こえた気がした。
今日、何度も夢見た光景だった。
ボールは――浮かない。
グラウンダーで、GKの脇をすり抜けていく。
出た。
一瞬遅れて、ネットが揺れる。
スタジアムが爆発した。
叫び声。泣き声。
歓声。どよめき。そして拍手。
実況の声が震えたまま響く。
「決めたァァァァァァ!!!」
「最後の試合!最後の1分!最後のゴール!!」
俺は天を仰ぎ、両手で顔を覆った。
熱いものが流れた。
笑いながら、泣いた。
仲間が次々に駆け寄ってくる。
皆が抱きしめてくれる。
これまでの10年分の感情が、一度に押し寄せた。
*
試合終了のホイッスルが鳴る。
俺は歩く。
ピッチの中央へ。
サポーターへ。
スタッフへ。
家族へ。
チームメイトが花束を持って現れる。
子どもたちが走ってきて、俺の脚にしがみつく。
スタジアムのスクリーンには、これまで決めたゴールの映像が流れ始める。
その最後に――
今のゴールが映された。
実況の声とともに。
「あなたのゴールは、永遠です」
観客席から、ゆっくりとコールが起こる。
最初は小さく。
やがて、スタジアム全体に広がっていく。
「ありがとう!ありがとう!ありがとう!」
俺はマイクを握る。
でも、言葉が出ない。
喉が震える。
胸が熱い。
涙が止まらない。
やっと、絞り出す。
「――こちらこそ。ありがとう」
それだけで精一杯だった。
*
ロッカールームに戻り、スパイクを脱ぐ。
このスパイクで、この芝を走った。
何度も倒れ、何度も立ち上がり、
今日――最後のゴールを決めた。
俺はスパイクをひとつ、手のひらに乗せて、
静かに呟いた。
「さよなら。最高の相棒」
*
帰り道、夜風が気持ちよかった。
スタジアムの照明はもう落ちていたが、
俺の心の中には、まだピッチの緑が広がっていた。
俺はもう、選手として走ることはない。
けれど――
あのゴールは、ずっと俺の中で生き続ける。
そしてきっと、誰かの記憶にも残り続ける。
最後のゴール。
それは終わりではなく、ひとつの物語の証だった。
俺は空を見上げ、そっと微笑んだ。
「またな――サッカー」
― 最後のゴール
試合が終わってから数時間。
スタジアムは静かになり、誰もいないピッチが月明かりに照らされていた。
俺はひとり、芝生に立っていた。
スパイクはもう脱ぎ、手にはボールを持っている。
そのボールは、今日――俺が最後に決めたゴールのボールだった。
観客の歓声も、仲間の涙も、引退セレモニーの拍手も、
すべてが遠くの記憶のように感じ始めていた。
静かだった。
こんなに静かなピッチに立つのは、プロになって初めてかもしれない。
俺はボールを置く。
ペナルティエリアの外。
いつも練習で蹴っていた場所。
深呼吸をひとつする。
振り返ると、ベンチには誰もいない。
照明は消えている。
ただ、月だけが見ていた。
俺はもう一度だけ、ボールに向かって助走をとる。
思い切り蹴るわけじゃない。
ゴールを狙うわけでもない。
ただ、最後に――この場所で、ボールを蹴りたかった。
音もなく、ボールは転がっていく。
ゴールネットに当たり、静かに止まった。
それを見て、俺は小さく笑った。
「よし」
それだけ呟いて、俺はスタジアムをあとにする。
二度と、このピッチでユニフォームを着ることはない。
でも――
サッカーが俺から完全に離れていくわけじゃない。
きっと、これからも誰かのゴールに心を震わせ、
少年たちがボールを追いかける姿に、自分を重ねる。
人生からサッカーが消えるんじゃない。
ただ、形が変わるだけだ。
スタジアムの出口に向かう途中、
ひとりの少年が、小さな声で叫んだ。
「また戻ってきてください!」
俺は立ち止まる。
振り返る。
たったひとりの、その声に――
俺の胸が再び熱くなる。
「うん。いつか、きっと」
そう言って、俺は夜の風に身をゆだねた。
最後のゴールは、終わりじゃない。
新しい人生の、最初の一歩だった。